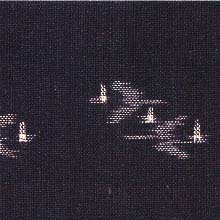産 地
岡山県津山市
特 徴
厚手の地風をもつ紺絣木綿織物。
小鼓、小扇など、弓ヶ浜調の素朴な絣模様と厚手の地風が特徴。
用 途
日常のしゃれた着尺地。
変 遷
明治以前は、自家用の木綿織物が織られる程度だった。明治中期になると、倉吉絣の技法をもとに絵絣の生産が始められたが、昭和になると衰退した。
昭和二六年に、織元である杉原博氏が地織絣の伝統を復興した。作州絣の名は、市場に出すためにそのときにつけられたものである。

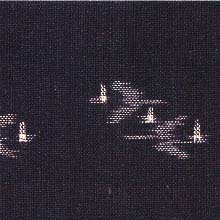

岡山県津山市
厚手の地風をもつ紺絣木綿織物。
小鼓、小扇など、弓ヶ浜調の素朴な絣模様と厚手の地風が特徴。
日常のしゃれた着尺地。
明治以前は、自家用の木綿織物が織られる程度だった。明治中期になると、倉吉絣の技法をもとに絵絣の生産が始められたが、昭和になると衰退した。
昭和二六年に、織元である杉原博氏が地織絣の伝統を復興した。作州絣の名は、市場に出すためにそのときにつけられたものである。